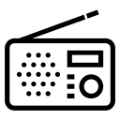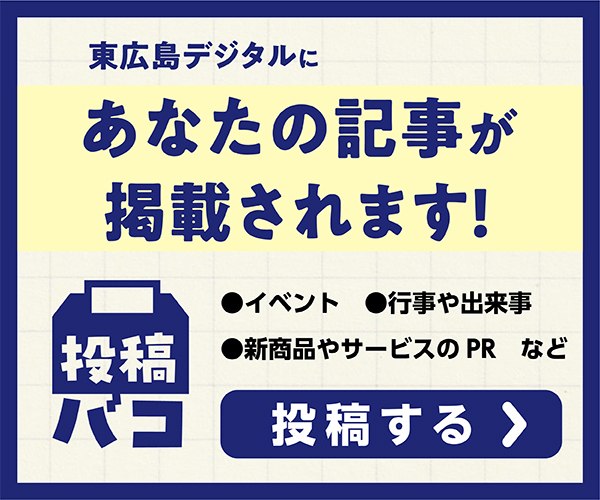文化芸術活動を支援するために、昨年12月に成立した「文化芸術振興基本法」をどう活用すべきか─法律の制定に向けて中心となって活動した衆議院議員・斉藤鉄夫さんが、文化芸術活動の現状を知るために映画・音楽など各界で活躍する方々を訪ねる特別対談シリーズ。
今回は、世界発のデジタル配信上映システムを導入したシネマコンプレックス「T・ジョイ」を全国展開するティ・ジョイの代表取締役社長であり、先日東映の代表取締役社長に就任した岡田裕介さんに、日本映画界の歴史や現状などを聞いた。
(CINEMANEWS:2002年7月発行号より)
映画界は自らの良識で物事を進めてきた。
斉藤:文化芸術基本法(基本法)の成立は、私にとって実現したい夢の一つでした。こうして成立した基本法を本当に生きた法律にするには、製作現場の生きた声を聞くことが最も大切なことだと思いお訪ねしました。まず、日本映画界の歴史や現場などをお聞かせください。
岡田:日本の映画界は、昭和30年代の始め頃には表現の自由という部分で国からかなりの規制を受けていました。そんな状況の中で映画会社は自主的に決め事を作って、それを守っていました。その代表的な例として「映倫」が挙げられます。15歳以下とか18歳以下などの未成年者の映画館入場を規制する、いわゆる「R指定」を管理してきた組織です。最近では「バトルロワイアル」という作品の上映を巡り国会でもR指定の問題が物議を呼びました。
映倫の運営について国の援助は一切受けておりません。我々が自主的に立ち上げ、我々が決めた約束事に則ってやってきたのです。このように、これまでの映画界は自らの良識で物事を進めてきた歴史があるのです。
斉藤:映画の製作サイドと国の接点は、これまではあまりなかったということですね。
岡田:そして1990年代に入ると外資系映画会社の進出が始まり、それまで保たれてきた秩序が崩れ始めたのです。私は、映画界こそが国内で最も早く外資系企業の参入が始まり自由化が進んだ業界だと思っているのですよ。そんな状況の中でも日本には国内の映画会社を守るための外交上の法律はなにもありませんでしたから、我々民間の映画会社は団結して外資系企業に対抗してきたのです。アメリカを例に挙げると「映画はアメリカのプロパガンダである」とか「アメリカの利益につながる」といった捕らえ方がされていて国は本気で支援している姿勢が見られます。日本とは大きな意識差があるのです。
今回の基本法では、美術・音楽・芸術などに関する創作活動を国に支援していただけるということで期待しています。実を言うと、日本映画界は過去に国から「映画鑑賞料金の内外価格差が開き過ぎだ」と注意を受けた経験があります。日本の映画館の料金はアメリカに比べて高いという理由で「料金の引き下げを実施しろ」というものでした。その時、私は冗談じゃあないと思い、もっと映画界の実情を知ってもらいたいと主張したことがありました。
斉藤:それだけ国と映画製作サイドに意識の違いがあったわけですね。
岡田:そうです。しかし、これまでに国からの支援がまったくなかったわけではないのです。文化庁の支援策として映画会社に製作費用として2,500万円の助成金が降りたこともありました。ですが、その助成金が映画製作のために有意義に利用されたかというと疑問です。製作サイドでは、せっかく2,500円をいただいたもののそれ以上の資金が調達できずどうしたものかという風潮がありましたからね。
それから、現在、経済産業省の主導でデジタルプロジェクターを公民館に普及させようとする動きがあるようですが、これにも疑問があります。T・ジョイで使用しているデジタルプロジェクターは12,000アンシ・ルーメンという画像の明るさを実現できる機種ですが、これくらいのレベルでなければ鑑賞に耐え得る画質は保証できないのです。性能的に中途半端なデジタルプロジェクターを普及させるのは、有意義な予算の使い方とは言えないと思うのです。
斉藤:そうですね。国はこれまでの姿勢を正し、ちゃんと映画界の実態を把握しなければなりませんね。
岡田:以前、国会議事堂を映画の撮影に使用できないかとお願いしたことがありました。もちろん会期中を避けて、空いている時期にあわせてです。結局「とんでもない。そんなことはできない」と断られましたが…。ニューヨークではあのセントラルパークの中でのカーチェイスを許可したりします。アメリカ映画のスケールの大きさに比べて国内作品が今一つ迫力に欠けるのは、こうしたことも背景にあるのではないかと思います。日本ではできないことが多すぎることを理解していただきたいですね。
斉藤:今回、基本法の構想段階で一番悩んだのは、国家と自由な独創的発想のバランスの在り方でした。例えば、国策にまったく対峙する可能性のある映画製作の活動を国が支援することにも成りかねないからです。では、なぜ国が文化芸術活動を支援するのかというと、1945年に第2次世界大戦が終わり、これからどうすべきかという時期にイギリスで芸術評議会が発足し初代会長には経済学者ケインズ(1883年〜1946年)が就任しました。ケインズは「民主主義は国民が自由な活動をするところに意義がある。その自由な精神を育む場が文化芸術ではないのか。それを国が支えることが国民の自由な活動を守ることにつながる」という論理を掲げました。今回の基本法もこの考えに基づいています。国は「金は出すが口は出さない」という姿勢でいなければならないでしょう。
岡田:今回、斉藤さんを中心にこのような基本法を実現していただき、映画製作に予算をいただけることは本当にありがたいことだと思います。とても意義のある法律が成立したのですから、映画作りの実情も良く理解していただいた上で予算の使い方を判断していただければ幸いです。斉藤先生とお話して本当に映画のことをご理解いただけているのだと確信しました。
斉藤:実際のところ有意義な予算の使い方についてはこれから本格的に研究しなければなりません。そのためにはやはり映画製作の現場からのご提案を重視して決定していかなければできないことだと思います。映画は総合芸術と言われています。1930年代にアメリカのルーズベルト大統領が行ったニューディール政策によって映画が勃興し、景気の底上げに一役買ったといわれます。そいう意味でも映画業界を引き上げていくことが景気全体を高めていく一つの力になるのではと期待しているのです。今日は興味深いお話を聞かせていただき大変勉強になりました。ありがとうございました。
岡田:こちらこそ、ありがとうございました。