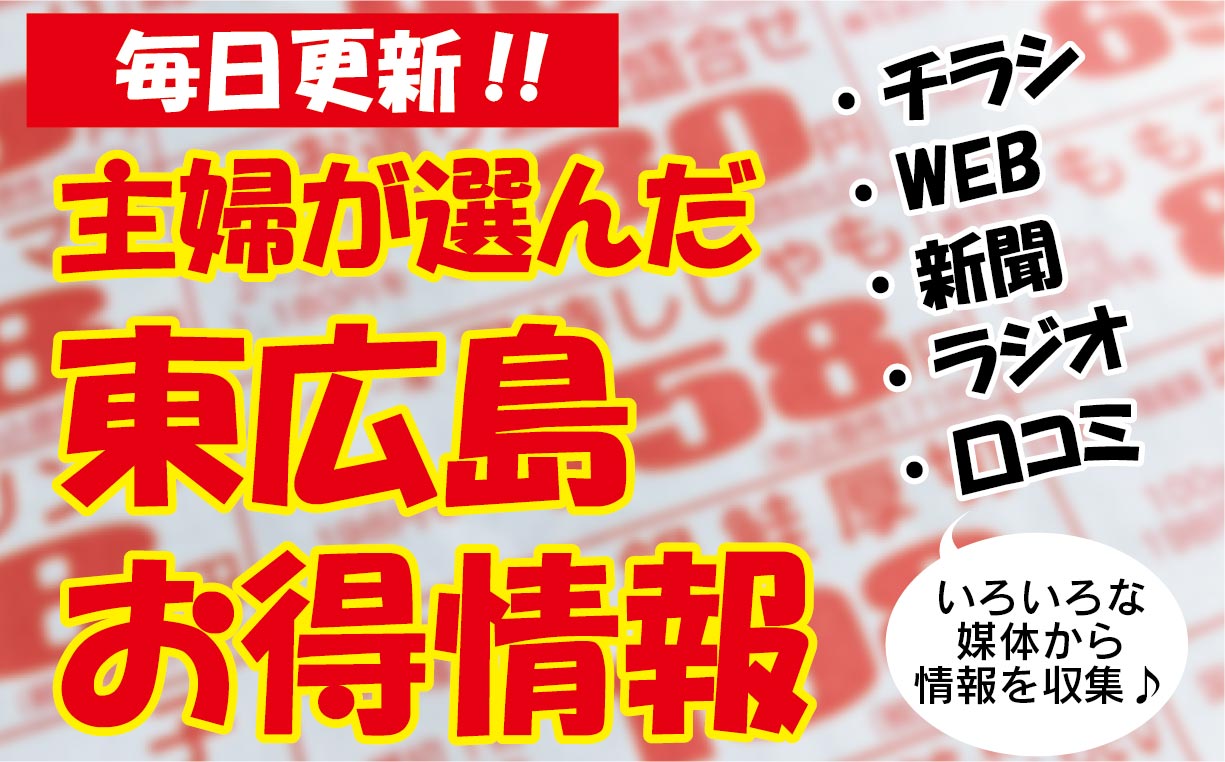※写真はイメージ
こんにちは!西条にある某飲食店の店長です!
私が日々グルメに携わる中で、見たり・聞いたり・感じたことを一筆論じて参ります🖌
今回は 「おせち」 のお話し。
「おせち」を漢字で書くと、「御節」という字になります。もともと『おせち』とは『節供(せっく)料理』で、五節供の料理のひとつなのです。
五節供とは、現代で言う一月一日の『元旦』、三月三日の『ひな祭り』や五月五日の『端午の節句』、七月七日の『たなばた』、九月九日の『重陽』(ちょうよう)の5つの節供(節句とも書く)をいいます。

五節供の料理とは、平安時代のころからおこなわれていた朝廷の『節日』に行われる行事『節会(せちえ)』で神様に供えたり、食べたりしたご馳走の事で、そのご馳走を『御節供』(おせちく)といい、それが後に『おせち』と略され、江戸時代に概略今の正月料理を意味するようになったと言われています。
おせちを重箱に重ねる意味とは
おせち料理を重箱に詰め、重ねて用意するのは、めでたさを重ねるという意味で縁起をかつぐためだそうです。

日持ちする料理が多いわけ
おせちの料理が日持ちするものが多い理由は、普段、よく食事を作ってくれる女性に正月三が日は休んでもらおうという意味にプラスしてもう一つ、「神様をお迎えした新年に台所を騒がせてはならない」とか「火の神である荒神を怒らせないために、正月に火を使わない」という平安後期からの風習のためだそうです。

つまりは神様と女性のための配慮ですね(平安時代は女性に優しかった?のですね。そういえば女性上位だった時代かも。
🔍まだ間に合う!東広島おせち特集
🔍過去のシリーズはコチラ

ナスには栄養がないってホント?【西条の有名飲食店・店長が論じます㊺
こんにちは! 西条下見にある飲食店の次郎丸、店長の森本です! 私が日々グルメに携わる中で、見たり・聞いたり・感じたことを一筆論じて参ります。 今回は「ナス」のお話し。 夏野菜と認識されることの多いナスですが、旬は6月から […]

イカがダイエット向きなの知ってました?【西条の有名飲食店・店長が論じます㊹】
こんにちは! 西条下見にある飲食店の次郎丸、店長の森本です! 私が日々グルメに携わる中で、見たり・聞いたり・感じたことを一筆論じて参ります 今回は「ミズイカ」のお話し アオリイカなら知ってます? 透明感のある色合いから […]

日本三大銘醸地の1つが「西条」なんです!【西条の有名飲食店・店長が論じます㉚】
こんにちは! 西条下見にある飲食店の次郎丸、店長の森本です! 私が日々グルメに携わる中で、見たり・聞いたり・感じたことを一筆論じて参ります 今回は「西条酒」のお話し 西条酒について & […]

栄養満点の河の豚って?【西条の有名飲食店・店長が論じます㉙】
こんにちは! 西条下見にある飲食店の次郎丸、店長の森本です! 私が日々グルメに携わる中で、見たり・聞いたり・感じたことを一筆論じて参ります 今回は「河豚」のお話し 「河豚」の名前の由来 […]

食感が鶏肉に似ている貝って何貝?【西条の有名飲食店・店長が論じます㉖】
こんにちは! 西条下見にある飲食店の次郎丸、店長の森本です! 私が日々グルメに携わる中で、見たり・聞いたり・感じたことを一筆論じて参ります 今回は「とり貝」のお話し 貝殻から伸びる黒い足が鳥のくちば […]

海の白雪姫ってどんな魚?【西条の有名飲食店・店長が論じます㉔】
こんにちは! 西条下見にある飲食店の次郎丸、店長の森本です! 私が日々グルメに携わる中で、見たり・聞いたり・感じたことを一筆論じて参ります 今回は「鱚(キス)」のお話し 別 […]

天下人の食卓に必ず使われてきた食材って何?【西条の有名飲食店・店長が論じます㉓】
こんにちは! 西条下見にある飲食店の次郎丸、店長の森本です! 私が日々グルメに携わる中で、見たり・聞いたり・感じたことを一筆論じて参ります 今回は「あわび」のお話し あわびの歴史 縄文 […]

「海の中の小さな家」と呼ばれる貝って何?【西条の有名飲食店・店長が論じます㉒】
こんにちは!西条下見にある飲食店の次郎丸、店長の森本です! 私が日々グルメに携わる中で、見たり・聞いたり・感じたことを一筆論じて参ります 今回は「サザエ」のお話し 「サザエ」名前の由来 […]

【シリーズ】西条の有名飲食店・店長が論じます【まとめ】
こんにちは!西条にある次郎丸の店長森本です! 私が日々グルメに携わる中で、見たり・聞いたり・感じたことを一筆論じて参ります🖌記事は随時更新中! ① コロナに負けない!感染症対策取組宣言している市内店舗は●件 ② 奈良 […]

寿司屋で米をシャリと呼ぶのは何故?【西条の有名飲食店・店長が論じます㉑】
こんにちは!西条下見にある飲食店の次郎丸、店長の森本です! 私が日々グルメに携わる中で、見たり・聞いたり・感じたことを一筆論じて参ります 今回は「寿司」のお話し 寿司の歴史 歴史は古く10世紀初めの […]