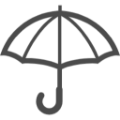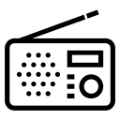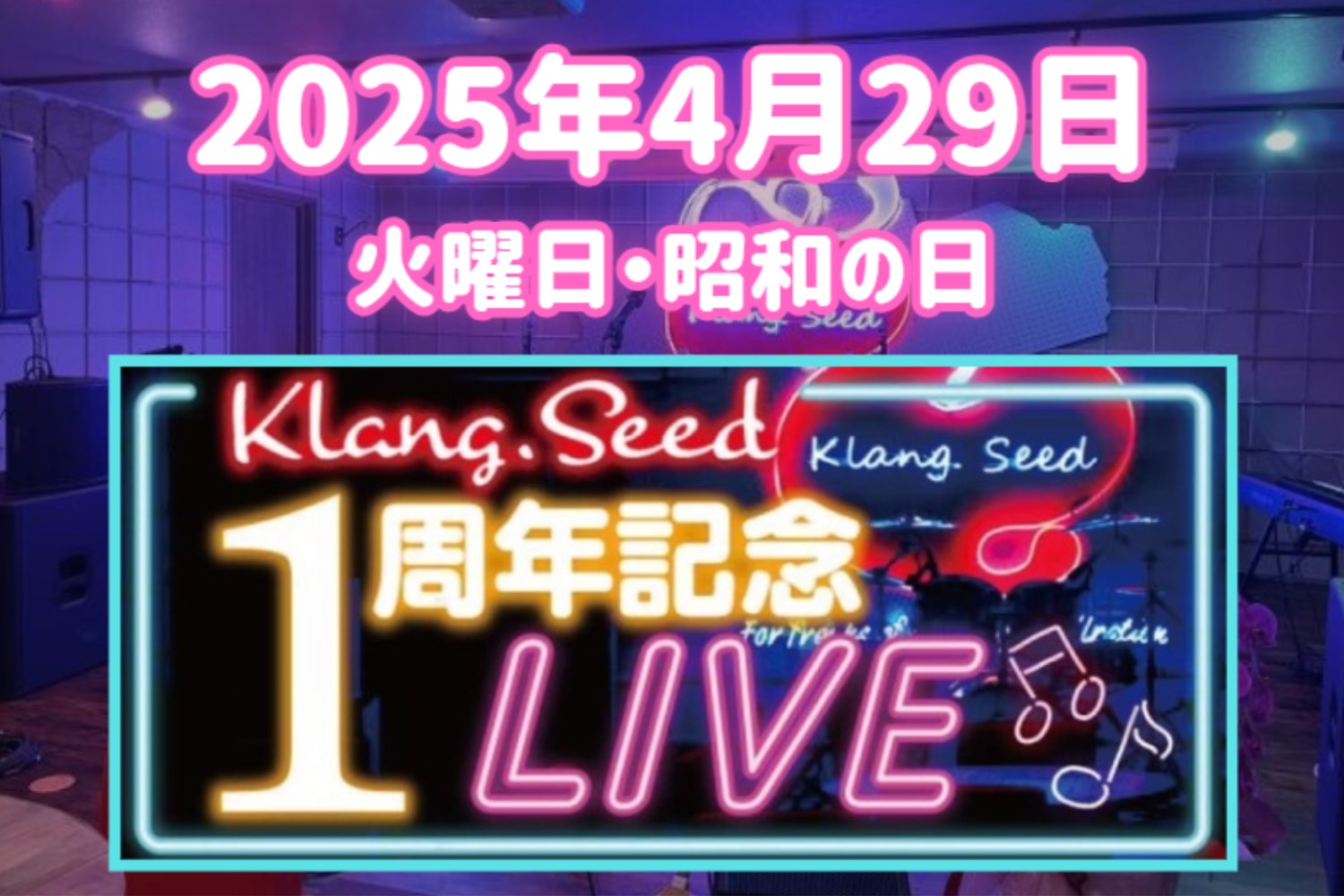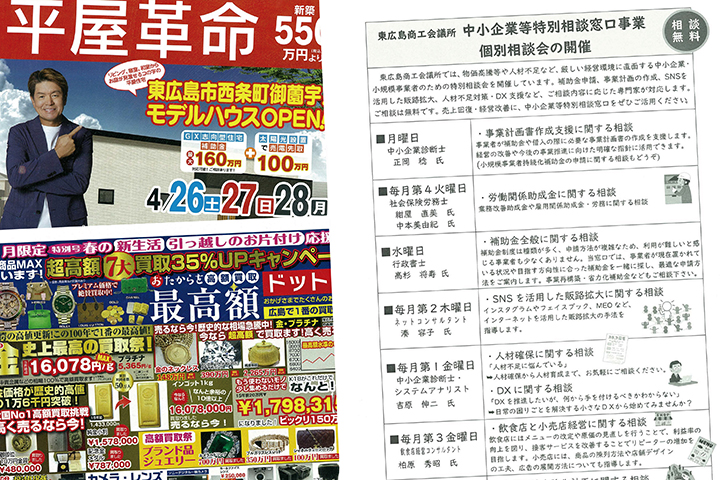仏壇仏具の技術を評価する第26回全国伝統的工芸品仏壇仏具展(全仏連など主催)が2月7~13日、伝統工芸青山スクエア(東京港区赤坂)で開かれ、仏壇販売店の「蓮池うるし工芸」(東広島市西条町西条東)の代表で、伝統工芸士の蓮池稔さん(63)が手掛けた仏壇が、伝統意匠部門で全国最高位の経済産業大臣賞に4期連続で輝いた。4期連続は全国初の快挙。

受賞作は「16号総開欅玉杢造(そうびらき・けやきたまもくづくり)」(高さ約149㌢、外幅約71㌢、奥行き約61㌢)。先人の技術を忠実に再現して2年がかりで制作した。販売価格は1320万円(税込み)。
伝統的工芸品の広島仏壇には7つの生産工程があるが、漆(うるし)を塗り金箔(きんぱく)を押す「塗師(ぬし)」は、県内では蓮池さんを含め3人しかいないという。
今回は、扉の前と横が開き屏風のような総開きの仏壇に挑んだ。80~180㌢サイズの仏間に入るように工夫しデザインしたという。丸く美しい木目がある最高のケヤキを使用し、表扉の木目はそのままに、裏扉は木目を生かしながら上から漆(うるし)を塗り金箔を施した。柱は、約1万本に1本しかない珍しく貴重な黒柿を使用。仏像を安置する須弥壇(しゅみだん)の透かし部分には、法隆寺(奈良県)が所蔵する仏壇の原点とされる国宝「玉虫厨子(たまむしのずし)」の技法を取り入れ、緑色に光るタマムシの羽、約200枚を約2㍉角に切って施すなど技術を駆使。広島仏壇の仲間7人と彫刻や金具、蒔絵(まきえ)など連携をもちながら分業し、蓮池さんが総合的に手間暇掛けて作業を積み重ね仕上げた。
総開きの摺漆(すりうるし)の扉や約5年がかりで漆を何百回も塗り重ね文様を表した堆漆(ついしつ)、銀を波状にして板の中に埋め込んだ銀線象嵌(ぎんせんぞうがん)などの伝統的技術が高く評価された。
蓮池社長は「3期連続最高賞を受賞し注目されていたので、力が入り過ぎて精神的にもきつい日々だったが、4連覇できてうれしい」と振り返り、職人の高齢化が進み技術が消えていくことを憂い「受賞した仏壇の技術や技法、知恵を多くの人に見てもらい、次の世代へ受け継ぐきっかけになれば」と期待を込めた。
(山北)