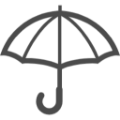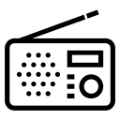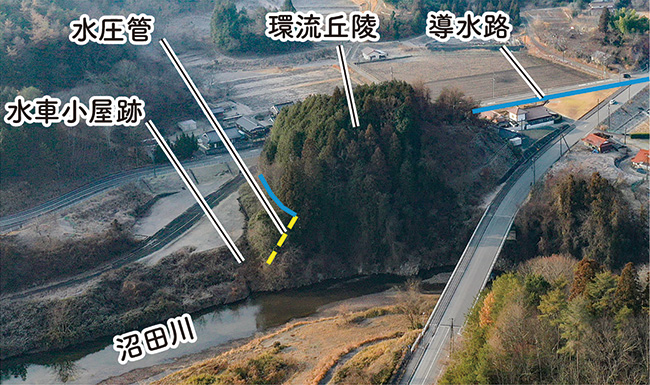東広島市が進める「Town&Gown(タウン・アンド・ガウン)構想」の柱の一つが、デジタル社会を見据えたTGOアプリの開発だ。TGOアプリとは何なのか。TGOアプリにかかわる東広島市の栗栖真一経営戦略担当理事と、韓国出身の留学生で地方経済の活性化を研究テーマに学ぶ、山口大経済学部3年生のイ ドンウさんに、TGOアプリへの思いをまとめてもらった。
データ収集し利用促進 今後改善を行う
東広島市経営戦略担当理事
栗栖 真一さん

伝えたい3つのテーマ
①TGOアプリの役割と必要性
②TGOアプリの誤解
③将来の展望
TGOアプリの役割と必要性
DX(デジタルトランスフォーメーション)が進んだ社会としてスマートシティという言葉が使われます。自動運転車などのハイテクな最新技術に目が向きがちですが、本質は、社会全体のコストや時間を削減するなど、生活をより効率的で便利にするために、データを活用することにあります。
例えば、携帯電話の位置情報で、その地域のニュースが自動的に表示されますし、通販で買ったものに関連した広告が表示されます。市が提供している市民ポータルサイトにおいても、住んでいる場所を登録することで、明日のゴミの収集内容を通知してくれます。
これらは、一例ですが、こうしたデータを活用したサービスは、既に私たちの生活の中に浸透しています。このようにデータを活用したサービスを提供するためには、誰が、どのように利用しているかなどのデータを収集・連携させていく必要があり、それが、TGOアプリの1つ目の役割で「デジタル社会に向けての基盤(プラットフォーム)」です。もう少し詳しく言うと、「①スマートシティの実証や実験を行うための基盤」とあわせて「②将来のスマートシティで使われるサービスを提供するための基盤」を作ろうとしています。
まずは、学生の利用者を増やし、データ収集をしたり、行動を分析したりする仕組みを組み立てる必要があります。
そのためには、学生に無理にアプリを使ってもらうわけにはいきませんので、「学生生活に欠かせない・便利な機能」を技術の実証とあわせて提供することによって、利用を促進していこうとしています。これが、TGOアプリの2つ目の役割「デジタルサービスを提供するための窓口」です。
実際のサービスの検討にあたっては、学生によるワークショップを開催し、いろいろなアイデアが出てきました。趣旨に賛同して集まった「スマートシティ共創コンソーシアム」に参画している企業が実証したいこともあります。法的な制約もあれば、誰がその開発費を負担するのか、また、運営費は誰が負担するのかといった課題もあり、実現できないものもありますが、国の補助事業や、企業からの寄付などを活用して、実証や実験を行いながら、少しずつ進めています。
TGOアプリの誤解
1つ目は、TGOアプリは、現状で完成ではないことです。「今のアプリの内容では使えないじゃないか」という声をいただきますが、そのとおりだと思っています。製品になってからリリースする民間のアプリと異なり、これから改善を行いつつ、ようやくサービスを加えていく段階になっています。
2つ目は、アプリが提供するサービスそのものの価値よりも、このアプリを使いながら、先端的な実証を行うことを呼び水として、様々な企業が集まり、地域の企業や市民生活に波及し、このまちの活性化につながることに、より価値があることです。
将来の展望
「TGOアプリ」の名前通り、Town(東広島市)とGown(広島大学)が中心となり、企業の知見も活用しながら、市民および学生のみなさまに使っていただけるアプリにしたいと思っています。具体的なサービスの充実については、学生自らが考え、授業の一環や起業を目指す学生が地元の事業者と連携しながら開発する仕組みを作る必要があります。開発のアルバイトやインターシップなどで地元への就職にもつながればと思っています。そうした中から、地域の課題に対応した新たなサービスが生まれ、市民の皆様に広く利用できるような仕組みづくりをしていきたいと思います。
TGOアプリの課題 学生の視点から提言
地域と企業の共創について研究している山口大学の留学生
イ ドンウさん

伝えたい3つのテーマ
①サービスの設計に課題
②企業・地域をつなぐ
③「作り手」「使い手」のコミュニケーション
取材を通じて分かったこと
取材を通じて、TGOアプリの課題は「利用者ニーズとの乖離(かいり)」「市議会の理解不足」「市の認識」であることが分かりました。多くの市議会議員はアプリの詳細を把握しないまま予算を承認しており、市も現状がうまくいっていないことを認識しつつ具体的な改善策をまだ示していません。
また、サービスの設計が「利用者のニーズ」ではなく「一方的な情報提供」に偏っているため、学生や市民にとっては魅力がなく、利用が進まない一因となっています。
学生目線から見た改善案
現在のTGOアプリは広島大学生を対象としており、他のTGO設置大学(近畿大学・広島国際大学)の学生や地域企業には十分なメリットを提供できていません。そのため、いくつかの改善策を提案します。
①対象範囲の拡大
全TGO設置大学の学生を対象に大学間交流を促進。「東広島市=学生の街」というブランドを確立します。
②学生間コミュニケーション機能の強化
匿名掲示板やアルバイトやインターン情報の提供を通じて、学生同士のつながりを強化。
③インセンティブ制度の導入
レビュー投稿や地域企業の利用でポイント還元を行い、学生と地域企業双方にメリットを提供します。
また、アプリへの賛同を広げることが重要です。アプリへの賛同は、市議会議員や他大学への理解促進、作り手と使い手の円滑なコミュニケーションを図るために必要です。これらの改善で、TGOアプリは「一方的な方向」から「東広島の学生・企業・地域をつなぐプラットフォーム」へと発展する基盤となると考えます。
私の感想
私が通う山口大学がある山口市にはTGOアプリのような学生、市民の生活を便利にする基盤のツールがなく、東広島市のTGOアプリはとてもいい取り組みだと思います。
ただ、今のままだと目的達成は難しいと思います。そのため、TGOアプリは将来像に近づくための機能だけではなく、学生と市民の生活が便利になる実用性のある機能を追加するなど、今のいくつかの状況を変える施策を行うべきです。そうすれば学生、市民の生活の質が向上し、全国でも注目を浴びる事例になると思います。
もう一つ、TGOアプリが使われていない原因としては「作り手」と「使い手」同士のコミュニケーションが足りなかったのではないかと思います。また、「作り手」同士のコミュニケーションも十分ではなかったためだと思います。
取材ノート
韓国出身で、地域と企業の共創について研究している山口大留学生のイ・ドンウさんがTGOアプリの課題について、関係者11人に取材。11人の本音の声を記した取材ノートを紹介する。
MEMO
TGOアプリ
2023年3月から運用開始。広島大学の学生を対象に学生生活を楽しく便利に過ごしてもらうためのサポートツール。
総閲覧数
2万6910PV(2023年3月10日~2024年12月31日)

学生情報の森「もみじ」
2009年7月から運用開始。広島大学の学生向けの情報を集めたポータルサイト。誰でも閲覧できる「もみじTop」と広大IDとパスワードでログイン後に利用できる「Myもみじ」で構成。Myもみじは大学からの休講や補講などの授業に関する連絡などを確認。
総閲覧数
258万9769PV(2024年4月1日~同年12月31日)
記者の目
TGOアプリを含めたタウン・アンド・ガウン構想の本質を、多くの市民知らない。知らないから無関心になり、市民の間には冷めた空気も漂う。
伝わらない理由は、行政のPR不足はもちろんだが、市民の代表である議員にも責任の一端はある。 聞けば、TGOアプリを本当に理解している議員は3分の1にも満たない。議場では、一部市議を除いて、論戦も低調だ。これでは、行政の過ちや方向の修正を正すことはできないだろう。
行政の過ちはTGOアプリ開発の方法論だ。現状で学生が使わないようなアプリに修正を加えないまま、今後も投資を続けるのはどうだろう。学生の存在が経済効果をもたらす東広島のまちの特長を考えたとき、TGOアプリを否定するものではない。ただ、どんなに優れたアプリでも、学生が利用するとは限らない。社会とはそういうものだ。
(日川)