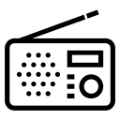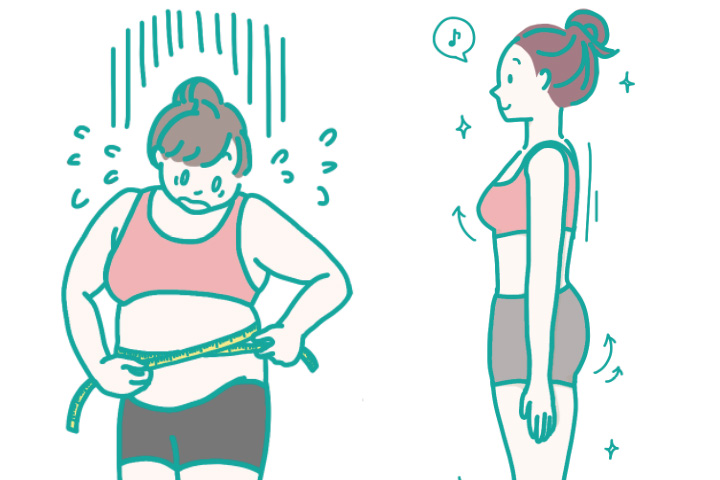25年ぶりのリーグ優勝と、日本シリーズ(日本ハム戦)出場で、多くのファンを呼び込み湧きに湧き返ったカープ本拠地のマツダスタジアム。そのスタジアムも、今シーズン中の熱気がうそのように、静寂に包まれる。スタジアム内に響くのは、来季に向かって秋季練習を行っている選手の声だけだ(若手は日南)。今シーズン、〝常勝軍団〟に向け新たな一ページを開いたカープ。今回は歴史を刻んだ「苦難の時代」を改めて振り返ってみた。
カープ球団の誕生は昭和25年だった。昭和20年8月6日の原爆投下からわずか5年。「廃虚の街に球団を」「復興への希望の光」と県民、市民の期待が寄せられた。
もともと広島は、戦前から中等学校野球が盛んな土地柄。広島商業、広陵が甲子園で何度となく全国制覇を果たし、「野球王国」の名をほしいままにしていた。
しかし、球団は誕生から苦難の連続だった。まず、各球団から広島の加盟、参入に「先行きが不透明」と反対の声が上がる。その声を「プロ野球の生みの親」といわれた正力松太郎(当時読売新聞社主)が一蹴してセントラル・リーグへの加入が認可された。だが、親会社を持たない球団はすぐに資金難に陥った。
親会社のない悲しさから銀行からの借り入れは不可能に近かった。個人や企業から集めた資金は1000万円に満たず、前途が危ぶまれたのは当然だった。初代監督は広島出身の石本秀一。広島商の監督を務めた石本は自ら金策に頭を下げて歩き回り、選手集めにも奔走した。
しかし、集まった選手は地元出身というだけで名もない人間ばかり。阪急の好意から5人の選手を譲り受けたが、全員がすでに峠を越えていた。総勢30人の中にはこんな選手もいた。戦前の名古屋金鯱(きんこ)時代に25勝を挙げたことのある中山正喜だ。金鯱の元エースとはいえ、肩を痛めて引退していた中山は、このとき故郷の松山に帰って喫茶店のマスターに納まっていた。8年のブランクがあったその中山を、石本監督は半ば強引に入団させたのだった。
いかに石本が選手集めに苦労していたかが分かる。巨人から「逆シングルの名手」として活躍していた広陵出身の白石勝巳が加わり、後に「小さな大投手」として名を馳せる長谷川良平が愛知の半田商工からルーキーとして入団。監督、コーチを含め総勢41人によって公式戦をスタートすることになったが、チームはいきなりリーグ除名の危機に追い込まれる。
昭和25年3月10日、「広島カープ」は初の公式戦に臨んだ。福岡平和台球場と下関球場に8チームが集結して、1シーズン20回総当たりのシーズンが開幕。初戦の相手は、同じくこの年からリーグに加盟した西日本パイレーツだった。(つづく)
プレスネット2016年11月12日号掲載